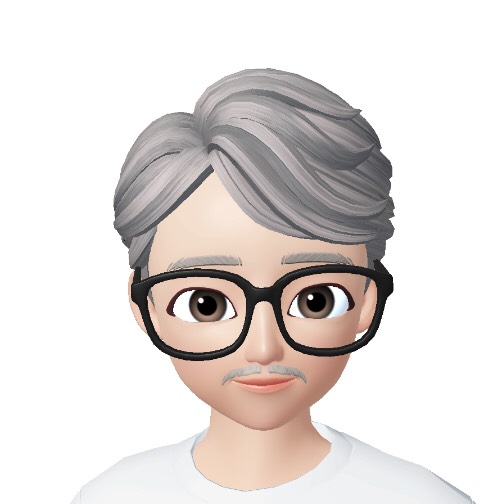
今回は、成長期のアンバランス状態が起こるクラムジーについてお話していこうと思います。
今話題のマッサージガン【BODYPIXEL】
身体のアンバランスとフラストレーション(クラムジー:Clumsy)
スポーツに取組む上で身体の成長期におけるクラムジーを知っておく必要性を感じます。
クラムジーは指令を出す脳が身体の成長に脳が修正出来ず軽微な誤りが生じることによるそうです。
バドミントンやサッカーで出会った子供たちを見ていて
成長期に入ったのかなと思えるのが、早い子で小学4年生くらいから始まり
遅い子は高校で始まる子もいました。
成長期に見られるのが身体のアンバランスで、数カ月の間に数センチ身長が伸びただけで今まで上手く蹴れていたボールも数ミリズレた場所を蹴っていて、上手く飛ばなくなり
身長だけでなく、腕や足も成長していて
今まで出来ていたものが上手くできなくなる現象を多くの子が経験します。
そんな時、子供たちは何故?下手になった?そんな感じで知らぬうちにフラストレーションを溜めていく。(クラムジー:Clumsy)
そんな時、試合中のミスに対して、何でそうなるの??と親や指導者もフラストレーションから、強い指導をしがちになります。
これは子供にとっても非常に辛い
自分でも分からないうちに出来たものが出来なくなっている。
どうしていいか分からない。
そんな状況を親や指導者が早く気づき、子供の不安を取り除いてあげることが大事なのだと思います。(成長期なんだから気長にいこうぜ~ みたいな感じ)
身体のアンバランスは、成長期が終わるまで何回か起こるので
子供への知識と耐えられるメンタルを作り上げていきましょう。
私の体験でお話すると
まず、バドミントンをやっていた娘たちを振返るとクラムジー状況に陥らなかったように思えます。
娘たちの身長は中学後半で止まり160cm届かないくらいで、成長のギャップが少なかったのことが一つ
それとバドミントンの特性からギャップが感じられなかったようにも思えます。
バドミントンは繊細なスポーツで夏と冬では、あの軽いシャトルが変わるのです。
シャトルは、気温が高いときはよく飛び、逆に気温が低いと飛ばなくなる。 夏場は飛びにくいシャトル(2番)、逆に冬場は飛びやすいシャトル(5番)を使う。
また気圧の影響もあり山間部などの標高の高い場所では、シャトルはよく飛びます。
また、体育館で朝試合をしている時と、午後ではシャトルの飛ぶ距離が違う。
微量の風にも影響されるなど、試合毎に環境が変わるので試合中に自ら修正しなくてはいけない。
常に環境の変化に対応しなくてはいけないスポーツなので、身体のアンバランスは試合だけでは見て取れないものだったように思えます。
また、女の子だったからと言うのもあるかもしれません。(良く分からん)
また、日常の練習も反復的な練習が多いので、成長期であっても脳の指令が身体の変化に合わせやすいのではないかとも思います。
グラムジーの副産物としてオスグッドや捻挫が多くなったとか身長や体重の変化から成長期で注意すべき時期か観察しながら見ていく必要性があると思います。
(クラムジーが出てくるかな・・・みたいな感じで観察)
次にサッカーなのですが、バドミントンと比較すると分かりやすいように思えました。
息子は小4の終盤から1回目の症状が始まる
少しづつ身体の成長が見て取れて、暫くすると走り方がアンバランスになった❓あれ?
そんなこともあり、今のうちに修正しないといけないのではないかと、単発で有料のかけっこ教室に入れてみると、指導者から言われたのが「クラムジーでしょうね~」と言われ
クラムジーの説明を受けた。
クラムジーの時期に走るフォームを固定化しようにも身体のバランスが悪いので早くなることは無い。今は静観する方が良い
そんなことを言われ、気づかされたのでした。
その時期はサッカーの試合でもミスが多く、試合後に指導者から「お前のせいで負けた!」と罵られ
保護者達は、「次は大丈夫だ!自信を持って」と同情の慰めが続いていた。
傍から見ていても不調が分かる
そんな状態で5年生へ突入
今振り返ってみると成長期のアンバランスが始まっていた状態
そんな状態であったが飛び級で1人だけ6年生のスタメンに入ってしまった。
4年生最後の春休みから、新6年生の遠征に参加、合間に5年生の大会に出るなど
クラムジー状態で身体を酷使している状態が続き
ケガも多くなり、5年生の6月に靱帯損傷
厳しいチームだったので、ぐだぐだ言われることを避けるためサッカー関連で名の知れた整形外科医に診察してもらい診断書とリハビリ計画書渡した。
私は今までリハビリ計画書を見たことが無かったが、最近はこうなんですね?
診断書では、治療に要する期間として2カ月程度、リハビリ計画書では練習再開は
治療後2カ月
息子と相談し、暫く休部する旨をコーチに伝えに!
コーチ曰く、
長い治療期間が終わってチームに溶け込むのに一苦労することが多いので
練習や遠征は極力参加して欲しいとのこと
また、月謝と遠征費も不要とのこと
この件についてはコーチの依頼を了承することにした。
成長期に保護者とその子供だけが注意していても足りない
スポーツ科学は日々進化しているので
指導者は子供の成長期に支障が出ないよう配慮していただければと思う次第です。
小学生から高校の間にクラムジーの症状が強く出て、スポーツを断念する子も数名見てきました。
おわりに私の経験や娘達を見ていて、スポーツを行う上で私の考えは1つ
高校2,3年で最高のコンディションで迎えること
現実は結構難しいですが
小学、中学で良い成績を残すことは将来戦っていく上で試合運びやメンタルにおいて
大きな力になってくれるものです。
良い成績を狙う活動はしていきますが、あくまでも私の考えは高校の2,3年で最高のコンディションに持っていく事
その時が一つの集大成と考えています。(その結果で将来を考えろ、みたいな)
その理由は、この時期が心身共に最高の状態であること
その状態で、自分の力量を判断して
スポーツをその先も行うのか、また、断念し他の道へ進むかの分岐点だと考えています。
私の経験も同様ですが娘たちを見ていても、高校1年の時より高3の時の方が身体能力は圧倒的に高くなっていました。
ですので、小学や中学で過度の期待から無理をして身体を壊し、好きなスポーツを継続できなくなるようなことが起きないよう切に願う次第です。
余談ですが、次女は中学時代ではケガで関東大会欠場、高校でも県シードを賭けた試合も棄権したことがあります。
本人も辛いと思いますが、棄権させることを容認できる指導者のチームに所属できたことが良かったかなとも思います。
片や長女は、弱小部活を都大会まで出場できるチームへ変貌させたので、顧問も経験が少なく、長女は無理をしすぎてしまった感があります。
二人とも高校3年でやり切ったことで、後悔は全くないようです。
私の考えである、高校2,3年で最高のコンディションで迎えること
は賛否両論あると思いますが、小学や中学で結果を求めるのではなく
回り道をしても、分岐点となる年代まで続けること
特に子供の成長期では、知らぬ間に子供を潰しかねないことがありますので
注意して見守って頂ければと思います。
ケガやクラムジーで苦労した選手と終わりのつぶやき
私の知っている範囲ですが
サッカーでは、長友選手の苦労も比較的有名ですが
本田選手も、クラムジーでJ下部に上がれなかったそうです。
ただ、高校で挽回しています。
バドミントンは有名選手の話ではないですが
娘達が高校最後の大会で上位の子を見ると万全な身体で試合に臨んでいる子は
非常に少ない、足や腰などを痛めていて
テーピングをぐるぐる巻きにしていて、足を固定
満身創痍のような状態で戦っている。自分自身との戦いでもある。
保護者も一緒に戦っているのだが、どのように見守るかですね
ただ、4種年代における技術や経験よる成長は著しいのですが、無茶をさせず身体の成長もシッカリ導いてあげて下さい。
本編に関連して、以下のブログも見ていただければと思います。




















コメント